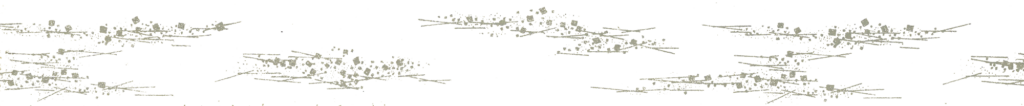中将の類(2)
―敦盛―
この曲は非常に素直な修羅物であるとともに、敗戦哀史といった情趣がすこぶる濃厚である。主人公敦盛は人も知る美少年で、それが戦場の花と散ったことは、悲壮というよりはむしろものの哀れを感ぜしめる一つの詩といいたい。一方また相手方の熊谷は、敦盛を討ったことから無常を感じて出家し、その菩提のために戦跡一の谷に来たところ、そこに敦盛の霊が現われ、二人は恩怨を超えて無限の法悦のうちに握手するというのがこの曲のテーマであって、このテーマが修羅物の典型的な型式のうちに巧みにまとめられている。
前場は、草刈男に化身した敦盛の幽霊が、ワキの旅僧を熊谷と知りつつ回向を頼みに現われるのが普通とやや違うが、そうしたことは心の奥底に持っているだけにして、表面の形は普通の前場のように謡ってよい。

後場では、次第に没落して行く平家の運命を描く[クセ]がおもしろい。この[クセ]で人間敦盛の哀れな心情を表現するのもよいが、それよりも平家という大きなものの没落の哀史に詩情をそそられながら謡いたい。最後に及んで今様をうたい笛を弄ぶのも敦盛らしく、また修羅物には極めて異例な〔中ノ舞〕をまうのも、この曲らしい曲趣を表わしているが、それらはすべて、修羅物の淡々たる謡い口を持しながら自然に情緒がにじみ出るように謡うのがよい。末段の修羅乗地は修羅物らしく強々とよく乗るべきだが、騒がしくなってはいけない。