[クセ]からが戦さ語りであるが、床几にかかったままさまざまな型を演じるところだから、キビキビと勇健に、しかも老将の落着きを失わずにしっかりと謡うべきである。語リは慌てず騒がずどっしりと謡い、それを受けた地もテンポを引きしめて底強く謡う。
「忠綱、兵を」以下、戦いが高潮に達したところは激しく乗って謡うべきであるが、「さるほどに入り乱れ」からは次第に敗戦の趣を表現し、辞世の「埋木の」云々には無念やる方なき沈痛な心持をこめなければならない。キリ地は調子を抑えて、悲運の老将の姿が草の陰に消えて行くさまを、しんみりした情調で表現すべきである。
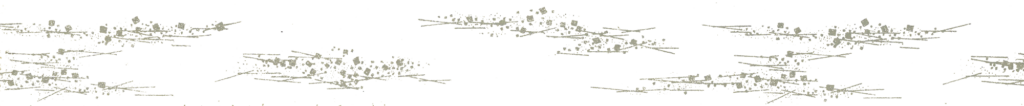
―実盛―
頼政と並んだ老武者の一つであるが、位の重い点では修羅物中随一とされている。人物の性格としては実盛は頼政とは比較にならぬほど単純である。身分も平宗盛の一部将にすぎないし、白髪を墨に染めて花々しく討死するのが念願といったしごく単純な人物であるが、能としてはなかなか凝った趣向に出来ていて、その表現においてすこぶる難曲とされている。